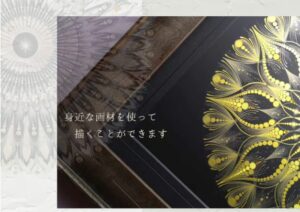曼荼羅アーティストの大迫弘美です。
主にボールペンを使って曼荼羅アートを描いています。

さて、曼荼羅の色にはどんな意味があるのでしょう。
実はその色には、深い仏教的な意味や心を映し出すチカラが宿っています。
無意識で深層心理に近づいてほしいので、講座内では色についてのレクチャーはしていません。
何気なく選んだ色に意味があり、その時に解放したい何かがあるからです。
曼荼羅アートの色彩心理的な効果を最大限に高めるには、色選びはその時の気持ちに委ねるのが一番なのです。
とはいえ、色には心と身体に働きかける作用があることは確か。
この記事では、曼荼羅における色の象徴的な意味と、アートセラピーとしての色彩の効果について、仏教的な視点と心理的な側面の両方からご紹介します。
曼荼羅以外でも役立つ場面があるかもしれません。

この記事で分かること
- 曼荼羅の色の役割
- 曼荼羅アートと色彩心理の関係
- 色の意味をアートに活かす方法
目次
曼荼羅における「色」の役割とは?
五正色(青・黄・赤・黒・白)と仏教の世界観

-Wikimedia Commons/File:Hevajra_Mandala.jpg
曼荼羅とは、密教における仏様の世界観を表したものです。
宇宙の構造が表現されているともいわれています。
仏教における五つの基本的な色、青(しょう)・黄(おう)・赤(せき)・黒(こく)・白(びゃく)を五正色(ごしょうじき)といいます。
五正色は、単なる色ではなく、宇宙を構成する五大元素や五仏と深く結びついているとされてます。
- 青(しょう)…空。無限や精神性。阿閃(あしゅく)如来
- 黄(おう)…地。安定・繁栄・実り。宝生(ほうしょう)如来
- 赤(せき)…火。愛・慈悲・情熱。阿弥陀如来
- 黒(こく)…風。変容・内観・浄化。不空成就(ふくうじょうじゅ)如来
- 白(びゃく)…水。浄化・純粋さ。大日如来
色は“意味”を持つ:方角と智慧
また、色は方角や智慧とも結びついていると考えられています。
智慧(ちえ)とは、物事の道理を理解し真理を見極める力、または悟りを開くための精神的な働きを指す仏教用語です。
色により、祈りの方向性やエネルギーの質を象徴します。
- 青(しょう)…東方。
大円鏡智(だいえんきょうち)。大きな円い鏡が万物の姿をありのままに映し出すように、すべての真実を明らかに見通す智慧 - 黄(おう)…南方
平等性智(びょうどうしょうち)。すべてのものには差別なく、平等であるという真理を悟る智慧 - 赤(せき)…西方
妙観察智(みょうかんざっち)。物事の個々の性質や違いを正しく見極める智慧 - 黒(こく)…北方
成所作智(じょうそさち)。なすべきことを成就させる智慧 - 白(びゃく)…中央
法界体性智(ほうかいたいしょうち)。法界(宇宙)そのものの本性を明らかにする智慧

- 青:ありのままを見る
- 黄:同じである(似ている)ことを知る
- 赤:個性、違いを知る
- 黒:やるべきことをやり遂げる
- 白:宇宙の真理(すべては一つ)であることを知る
こんな感じかな
曼荼羅の色で感じる祈りと調和

曼荼羅の色彩には、それぞれに意味とエネルギーが宿っていることが分かってきたかと思います。
青・黄・赤・黒・白、そして金や銀、紫など——これらの色は、ただ美しさだけでなく、私たちの心や魂に直接働きかける“祈り”そのものです。
みずから曼荼羅アートを描くときも、私たちは無意識のうちに今必要としている色を手に取ります。
たとえば、癒しを求めるときには青や緑、内なる強さを必要とするときには赤や金、繁栄を願う時には黄を手にします。
色を通して自分自身の願いを表しているのです。

曼荼羅アートと色彩心理の関係
色彩心理学とは、色が私たちの心や感覚に与える影響を明らかにする学問です。
たとえば、青を見ると心が落ち着いたり、赤に元気をもらえたりするのは、色が脳や感情に働きかけているからです。
これは一時的な気分だけでなく、私たちの行動や選択、気づきにまで影響を与えるチカラを持っています。
曼荼羅アートでは、この「色のチカラ」が自然と現れます。
何気なく選んだ色が、実は今の心の状態や、求めている癒しのテーマを教えてくれることもあります。
だからこそ、曼荼羅アートを描くことは“色を通じて自分と向き合う”セラピーになりうるのです。
色は心の状態を映し出す鏡〜色彩心理学の視点から〜

色にはそれぞれ、私たちの心と身体に働きかけるチカラがあることが、色彩心理学の研究からも明らかになっています。
曼荼羅を描くときに無意識で選ぶ色は、「鏡」のようにその時の心理状態を映します。
たとえば、青は副交感神経を優位にし、気持ちを落ち着かせてくれる効果があります。
そのため、緊張しているときや、不安を感じているときに青を使いたくなることがよくあります。
赤は交感神経を刺激し、エネルギーを高めたり、行動を促したりする働きがあります。
無意識に赤を選んでいるときは、「前に進みたい」「何かを変えたい」といった内なる意欲が芽生えていることも。
このように色はただの視覚情報ではなく、脳や感情に直接影響を与えることができる“波動”なのです。

色を選ぶことが「自分と向き合う」ことに

曼荼羅アートにおいて色を選ぶ行為は、色彩心理のセルフチェックそのものです。
たとえば、オレンジに惹かれるなら、それは「つながり」や「喜び」を求めている心の表れかもしれません。
緑に安心を感じるときは、調和や休息、安定を求めているサイン。
紫が気になるときは、感受性や直感力が高まり、精神的な癒しや高次の意識への憧れが強まっている状態です。
色彩心理学では、このような色の好みが人の気分や性格傾向、心身のコンディションと密接に関わっていると考えられています。
曼荼羅に色を塗りながら「なぜ今日はこの色を選んだんだろう?」「この色の曼荼羅アートが気になるのだろう」と問いかけることで、心の奥にある“自分の本質”に気づくことができるのです。
セラピーとしての曼荼羅アートの魅力
色彩心理学の分野では、色を使ったアートは「非言語的セラピー」として注目されています。
とくに曼荼羅アートのように規則的で繰り返す模様に色をのせていく行為は、安定感をもたらし、心が整う効果が考えられます。
頭で考えずに直感で色を選んで描いた曼荼羅アートは、本人が驚くような「内面の声」が込められることがあるのです。
実際にモヤモヤしているときに描くと、「気持ちが落ち着いた」「リセットされた気がする」と感じる方が多いのも、集中することによる瞑想効果に色が持つ心を整えるチカラがプラスされるからです。

曼荼羅アートは、描きながら自分と対話し深い癒しへと導く色のセラピー。
自由に色と遊ぶことで、みずからのチカラで本来の自分と出会うことができるのです。

色の意味を知って、曼荼羅アートをもっと楽しもう
曼荼羅アートに色の意味を取り入れる方法

曼荼羅アートを描くときに色が持つ意味を理解して取り入れることで、作品に自分の意図や願いを込めることができます。
色彩は、私たちの感情や思考、波動に影響を与えるといわれています。
どんな気持ちで制作したいか、どんな願いを込めたいかを意図して色を選ぶことで、曼荼羅アートに「願いを叶えるツール」としての役割を持たせることができます。
たとえば、以下のような気持ちに合わせて色を選ぶのがおすすめです
- リラックスしたいとき:青や白などのクールカラーは、気持ちを落ち着かせ、心を穏やかにしてくれます。
- 活力を得たいとき:赤やオレンジなどの暖色系は、内なる情熱や行動力を引き出し、エネルギーを高めてくれます。
- 心の安定を求めるとき:緑や黄色などの自然を感じさせる色は、安心感や調和をもたらしてくれるでしょう。
このように、色の効果を取り入れて描くことができるのですが、それよりも大切なのは、今の自分が「使いたいと感じる色」を選ぶことです。
直感的に惹かれる色こそ、自分の心の声。
色には意味があるとはいえ、それにとらわれすぎる必要はないのです。
曼荼羅アートは、自分自身です。
線や形、色を通して本来の自分を向き合うツールです。
色彩心理学をヒントにしながら、直観に委ねて自由に表現しましょう。

心理的効果や願いに合わせた色の選び方
色には私たちの心と身体に働きかけるチカラがあります。
目的に合った色選びが、描く曼荼羅アートをパワーアップさせることができます。
以下を参考に願いを込めた曼荼羅アートの制作にもチャレンジしてみましょう。
主な色の心理的効果と対応するテーマ:
| 色 | 心理的効果 | 対応する気持ち・テーマ |
|---|---|---|
| 赤 | 活力・情熱・生命力 | 行動力、変化、怒りの浄化 |
| 青 | 落ち着き・静けさ・誠実 | 不安の解消、集中力 |
| 黄 | 希望・明るさ・知性 | 自信、ひらめき、楽しさ |
| 緑 | 安定・安心・調和 | 癒し、休息、再生 |
| 紫 | 精神性・神秘・内観 | 感受性、直感、浄化 |
| 白 | 純粋・清らかさ | スタート、リセット |
| 黒 | 内観・守り・変容 | 深層意識との対話 |
自由に感じて、自分だけの曼荼羅を描こう
曼荼羅には「こうでなければならない」という決まりはありません。
色の意味を参考にしながらも、自分の感性に素直になって、自由に色を選び、自由に描いてみましょう。
それこそが、心を整え、癒しへと導く曼荼羅アートです。
曼荼羅(曼荼羅アート)に使われる色には、仏教的な象徴としての意味と、色彩心理学に基づく心への働きかけ、両方のメッセージが込められています。
色は、私たちの心や魂と深くつながる神聖なツール。
曼荼羅アートを通して、自分自身の内なる宇宙と静かに向き合う時間を持つことができます。
色を通じて、自分を癒し、整え、本来の自分を表現しましょう。
まとめ
仏教における五つの基本的な色、青(しょう)・黄(おう)・赤(せき)・黒(こく)・白(びゃく)を五正色(ごしょうじき)という。 五正色は、五大元素(空・地・火・風・水)、五仏、方角、智慧と関連がある。 ※智慧(ちえ)とは、物事の道理を理解し真理を見極める力、または悟りを開くための精神的な働きを指す仏教用語
空。無限や精神性。阿閃(あしゅく)如来
東方。
大円鏡智(だいえんきょうち)。大きな円い鏡が万物の姿をありのままに映し出すように、すべての真実を明らかに見通す智慧
地。安定・繁栄・実り。宝生(ほうしょう)如来
南方。
平等性智(びょうどうしょうち)。すべてのものには差別なく、平等であるという真理を悟る智慧
火。愛・慈悲・情熱。阿弥陀如来
西方
妙観察智(みょうかんざっち)。物事の個々の性質や違いを正しく見極める智慧
風。変容・内観・浄化。不空成就(ふくうじょうじゅ)如来
北方
成所作智(じょうそさち)。なすべきことを成就させる智慧
水。浄化・純粋さ。大日如来
中央
法界体性智(ほうかいたいしょうち)。法界(宇宙)そのものの本性を明らかにする智慧
色には私たちの心と体に働きかけたり、心理状態を表す。 (例) 何色を選ぶかで、自分でも気がついていない”自分の本質”に気づくことができる。
①色が持ち意味を理解しそれを取り入れることで、作品に自分の意図や願いを込めることができる⇒曼荼羅アートが「願いを叶えるツール」になる ②自分と向き合いたいとき、あるいは心を整えたいときには以下のように、何も考えずに無意識で選ぶとよい。